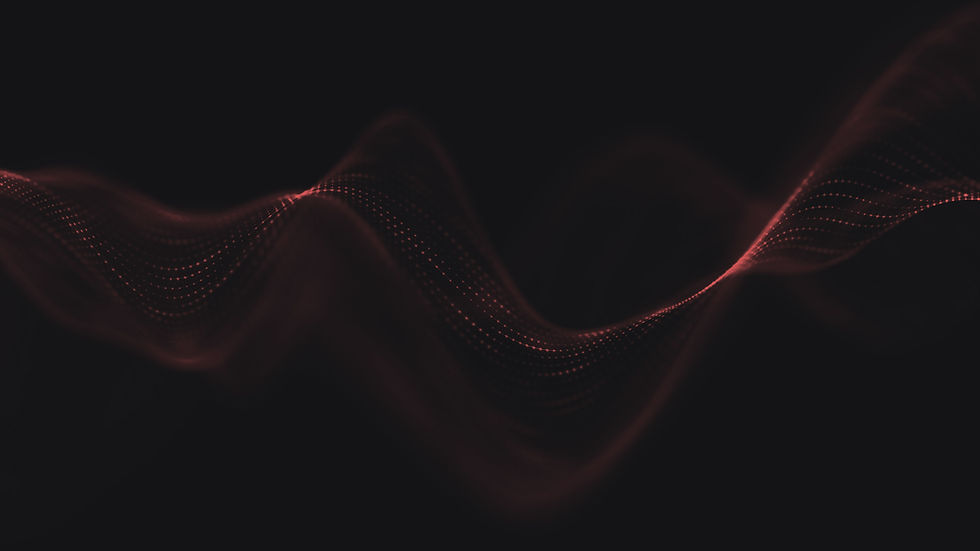
ミッション
たとえば、生成AIは急速に進歩を遂げていますが、誰もが容易にアクセスできるとは限りません。
AI・数学のチカラを誰もが容易に利用できる社会の実現、誰にでもやさしいAIを日本にもたらす、それが私たちのミッションです。
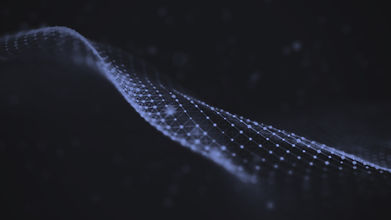
ビジョン
従来型ITのテクノロジーを超え、AI‧数理モデル‧クラウドに特化したハイレベルな事業領域を基軸として、DX化が遅れている日本社会に貢献すると同時に、次世代のハイレベルエンジニアを独自に育成します。
また、この日本ならではのきめ細やかなSaaS事業を海外にも展開することが私たちのビジョンです。
本当に必要なAI人材とは、技術力で計れるものではありません。
社会でAIや数理最適化の恩恵にあずかれない人々を思いやって、それらの利用者に惜しみなく恩恵を提供できるような「マインド」こそ重視されるべきです。
「誰にでもやさしいAIを日本にもたらす」
我が社のポリシーはこの教育方針に焦点をあてています。
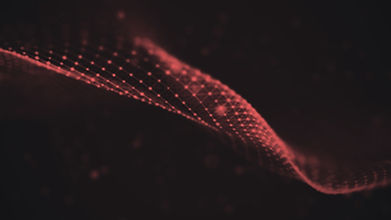
ポリシー
創業30年と新たなスローガン
おかげさまで、2027年、シーライヴ株式会社は創業30年を迎えます。これもひとえに、お客さまをはじめ、取引先の皆さま方、当社の従業員、そしてインターネットやAIを利用してくださる世界中の人々の恩恵であると感謝いたします。
AI for All
これを機に、当社の新たな方向性を示すスローガンを策定しました。
このスローガンの意図するところは、「難しい」「危ない」という印象を持たれがちな「AI」テクノロジーを世の中の誰もが容易で安全に利用できる社会実装をめざすところにあります。
AIは「特権階級」のものではありません。社内生活の中ではさまざまな難問が立ちはだかります。世代間のギャップや貧富の格差も存在します。それでも人類は希望を胸に秘め、幸福を目指して生き続ける存在であらねばなりません。
そのためにAIをひとつの解決策・ツールとして生かしていくことが当社の使命です。
古代ギリシャ、江戸時代、そして現代
さらに、私たちの理念と矜持について説明を続けます。
“I know nothing except the fact of my ignorance.”
これは「無知の知」で知られる古代ギリシャの哲学者ソクラテス(紀元前4世紀頃)の言葉です。彼は「私は自分が無知であるという事実以外に何も知りません」と言っています。
現在、私たちは高度に情報化された世界で暮らし、AIの進化はとどまるところを知りません。世界情勢や政治家の選挙が、ネットで左右されてしまうような時代に突入しました。このような様相はとどまるところを知らず、さらに高度化・グローバル化していく可能性があります。
いまの私たちがソクラテスと語り合えば、彼は何を思い、何というのでしょうか。現代科学、現代社会、そしていまのAIシーンは、彼に驚きを与えるとともに、一方で彼に新たな哲学上の思索をもたらすかもしれません。
すでに宇宙空間にまでおよんでいる科学技術の水準は、私たちに一種の優越感や思い過ごし、万能感を生み出しているのかもしれません。
「江戸時代よりも現代のほうが進歩している」というイメージは、確かにそうである反面、姫路城や風神雷神図、歌舞伎や文楽、満開の桜に触れたとき、そのイメージは感嘆と畏敬の念によって、いとも簡単に覆されてしまいます。これはAIでは体験できない人間そのものだからです。
現在のAIシーンにおいてもこうした感覚がきわめて大切なのではないか、当社はそう考えています。「AI化がすべて」ではなく、あくまで「きかっけ」「道具」であると。
情報は存在するだけではただのデータです。しかし、そこにかけがえのない価値を見い出すこともできます。それはすなわち私たち人間のなせる業です。
AIは万能ではない、人間は失敗も犯す、しかし、それでも人間は生きて前進していく、その手助けのひとつがAIテクノロジーであると考えます。
我が社の方針①
安全策にばかり溺れるな。リスクを取る選択も必要。

スティーブ・ジョブズ(Steven Paul “Steve” Jobs, 1955~2011年)
「安全にやろうと思うのは、一番危険な落とし穴なんだ。」とは、かのスティーブ・ジョブズの名言です。Apple社が「iPodミニ」で空前の大ヒットのまっただ中のとき、スティーブ・ジョブズは売上げ絶頂期にも関わらず、iPodミニの販売を中止し、新商品の「iPodナノ」の開発を打ち出しました。
結果はご存じの通りさらなるヒットを生み出しました。安定した状況にあっても、リスクを恐れず貪欲にさらなる一手を打って、イノベーションを起こすこの精神がそこにあります。
我が社の方針②
「猿まね」と嘲笑っているうちに、追い越される。
まずは「猿まね」から堂々と始めよう。
狂人の真似まねとて大路おほちを走らば、即ち狂人なり。悪人の真似まねとて人を殺さば、悪人なり。驥きを学ぶは驥の類たぐひ、舜しゆんを学ぶは舜の徒ともがらなり。偽りても賢を学ばんを、賢といふべし。
これは鎌倉時代末期の随筆家・吉田兼好(1283~1352年)の言葉です。
現代語訳すると、「狂った人の真似」と言って国道を走れば、そのまま狂人になる。「悪党の真似」と言って人を殺せば、ただの悪党だ。良い馬は、良い馬の真似をして駿馬になる。聖人を真似れば聖人の仲間入りが出来る。冗談でも賢人の道を進めば、もはや賢人と呼んでも過言ではない、という意味です。
吉田兼好は、随筆『徒然草』の中で、度々「まね」について述べています。人まねをバカにしている人ほど実は能力が伸びない、むしろ他人からバカにされてもそれを恥と思わず、愚直にやっていく人こそ後年化けるんだと喝破しています。とても鎌倉時代のエッセイとは思えません。現代でも光って読める内容です。

吉田兼好(1283~1352年)
AIは手段、目的は私たちの中に
“彼を知り己を知れば百戦殆うからず。彼を知らずして己を知るは一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば戦う毎に殆うし。”
これは、中国春秋時代の思想家孫武(紀元前5世紀頃)の著作とされる兵法書「孫子」の一節です。彼は「相手のことをよく知り、自分のこともよく知っていれば、戦いに恐れはない。相手のことはよく知らないが、自分のことをよく知っている場合は、勝負は五分五分である。相手のことも、自分のことも知らない場合は、連敗は必定」と語っています。
19世紀はじめのプロシアの将軍・クラウゼビッツは、その著書『戦争論』の中で、「戦争はあくまで手段であり、目的は政治的な諸関係・・・手段は決して目的を離れてはいけない」と述べています。
これらは、いずれも私たちに戦略の要諦を示してくれています。消費者やお客さまのことを知らずして、あるいは、手段に埋没してしまい目的を忘却してしまう、高度にAI化・情報化され、スピードとグローバル化が盛んないま、当社はこの視点を意識し続けたいと思います。
当社は、AIが手段であり目的ではないこと、そして、その目的を定め前進していくのはあくまで人間であること、その人間はときに失敗もすることをいつも心にとめて仕事にあたります。
「現代が万能である」と思い過ごさず、失敗を冷静に語れることこそが、人にとっての最大の成功であると考えます。同様に、それを無理せず、楽しみながら持続していくことに意義があるのだと考えます。
次の半世紀、1世紀に向けて、当社はさらに歩みを続けます。これからも、また多くのお客さま・取引先・AI利用者と出会えることを夢見ながら、時には寄り道しながら旅に出かけます。
我が社の方針③
失敗の繰り返しこそ上達への近道
20世紀最大の科学者ともいわれるアルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)はこういっています。
It is a miracle that curiosity survives formal education.
正規の教育を受けて好奇心を失わない子どもがいたら、それは奇跡だと。
いま世間でよくいわれている“イノベーション”とは、世の中で<今まで当たり前>のように扱われてきたことを破壊するぐらいのインパクトを指します。新しい時代の到来にはそうした試練が必要なんですね。それは世界史を読み解くと、いくらでも記されています。

代表取締役 久保田浩嗣
若いみなさんには、今まで当然といわれたやり方や考え方を"破壊"するくらいの意気込みと、既存のルールや方法に疑問をもって就職活動をしてほしいと思いますね。もちろん、もしインターンシップの機会があれば、そのように指導・サポートをしたいと思います。
私は若い人たちとの議論が大好きなんです。大人への不信や社会の不条理についても、どんどん意見を聞きます。もちろん私も負けずに大いに反論しますがね(笑)。
ようは、その人ごとの生きる力だと思うんです。これで個々人の世界観は大きく変わりますから。スキルや知識は二の次。スキルは時間と経験の中で誰にでもついてくるものです。個人差はありますがね。入試のように<測れるスキルの問題>ではなく、自分の<生きる力そのもの>に注目して欲しいと思います。
サッカー日本代表の本田圭佑選手は、かつて自分を評してこう言っているんです。
「俺ってすごくポジティブな性格だけど、裏を返せば、実はすごく不安な性格なんです。不安だから努力しようと思う。簡単に言えば強がっているんですよ」。私なんてかなりこれに近いですよ。
みなさん、まずは卵を割りましょう。そうでないとオムレツはつくれませんよ。
シーライヴ株式会社 代表取締役 久保田浩嗣